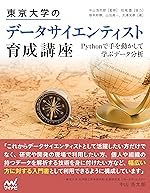-
-
記事では、ChatGPTの生成能力に関する疑問が投げかけられています。
VTuberになるためにキャラクター画像の生成も、簡単にできることが示されています。
YouTubeのサムネイル画像の生成についても触れられています。
-
-
-
OpenAIがChatGPTの基盤モデル「GPT-4o」に画像生成機能を統合しました。
テキストのレンダリング精度や複雑な指示への対応力が向上し、実用的な表現が可能になりました。
ChatGPTのPlus, Pro, Team, Freeプランのユーザーはデフォルトの画像生成機能を利用できます。
-
-
-
Hono v4.7.0からv4.7.5までのリリースノートが紹介されています。
Proxy Helper、Language Middleware、JWK Auth Middlewareなどの新機能が追加されました。
Standard Schema Validatorによるバリデーション機能も強化されています。
-
-
-
米国の研究チームが人間の認知能力に関する新たな研究を発表しました。
研究によると、認知能力の低下は老化ではなく、脳を使わないことが原因である可能性が示唆されています。
読み書きや計算能力を頻繁に使う人は、高齢になっても認知能力の低下が見られないことがわかりました。
-
-
-
GoogleがAndroid OSの開発を今後完全に非公開化するとのことです。
これまではオープンソースプロジェクトを通じて公開開発されていましたが、来週から社内の内部ブランチに一本化するそうです。
開発の効率化が目的ですが、透明性の低下も懸念されます。
-
-
-
この記事では、GPT-4oとGemini-2.0の画像生成能力の背景にある技術を解説しています。
拡散モデルから自己回帰モデルへの進化、Any-to-Anyモデルの概念、そして具体的なモデルの構造に焦点を当てています。
これらのモデルがどのようにして多様なデータを処理し、高品質な画像を生成するのかを考察します。
-
-
-
生成AIでジブリ風画像を生成しSNSに投稿する事例が増えています。
オープンAIの画像生成技術がきっかけです。
既存の画像や写真をアニメ風に加工する利用が広がっています。
-
-
-
この記事では、LLMアプリケーション開発環境の構築事例を紹介しています。
開発プロセスにおける課題を解決するための3つのアプローチを解説しています。
Prompt Storeの開発、Langflowの導入、デプロイシステムの構築について詳しく説明しています。
-
-
-
ChatGPTがAIモデルと外部サービスを繋ぐ規格「MCP」に対応することが発表されました。
この規格はAnthropicが提唱し、Microsoftなども採用する業界標準になる可能性があります。
OpenAIの対応により、AIサービス開発の効率化が期待されています。
-
-
-
Playwright MCPは、自然な日本語のコマンドでブラウザ操作やAPIテストができるツールです。
初心者でも簡単にE2Eテストを導入でき、テスト担当ではない企画担当の方もテストを作成可能です。
UIとAPIテストを組み合わせることで、リリース前の重大なバグを早期に発見できます。
-
-
-
動画編集ソフトAviUtlに関するまとめ記事です。
AviUtlは古いソフトだが、いまだに使われている現状が解説されています。
代替ソフトを考える難しさにも触れています。
-
-
-
paypayの決済取り扱い高10兆円というニュースに対する意見。
年間10兆円の取引を支えるシステム担当者は楽ではないだろうと推測。
大規模システム運営の裏側を想像させる内容です。
-
-
-
ChatGPTに低品質な画像を依頼した結果がまとめられています。
ユーモアあふれる画像が生成され、話題になっています。
林家GPT亭と名乗れるレベルというコメントも。
-
-
-
小中学生向けのAIお悩み相談サービスの実証実験で、満足度が90%超えを記録しました。
相談件数は人間のカウンセラーより10倍以上多く、AIへの相談のしやすさが示唆されています。
AIは初期接点として機能し、必要に応じて適切な支援につなげる役割が期待されています。
-
-
-
GoogleドライブでGeminiのPDF要約・内容理解機能が、日本語を含む20以上の言語に対応しました。
これにより、多言語のドキュメントをより効率的に扱えるようになります。
特に長いPDFの内容把握に役立ちそうです。
-
-
-
消費者庁がパソコン工房に対し、景品表示法違反で措置命令。
期間限定と謳った特典が、実際には期間後も同様に提供されていた。
ユニットコムは謝罪し、管理体制の見直しと再発防止を約束。
-
-
-
GIGAZINEで、充電不要で一生使える「ベータボルタ電池」が登場したという記事が掲載されました。
この電池は、放射性物質を利用して発電する仕組みのようです。
詳細は記事で確認できます。
-
-
-
iPhoneで「コンパクトな増田」を利用する方法を紹介します。
通常版よりも表示がコンパクトで読みやすいです。
手軽に増田を楽しみたいユーザーにおすすめです。
-
-
-
アップルが謎の新型PC「Lumon Terminal Pro」を発表しました。
しかし、これはApple TV+のドラマ「セヴェランス」のプロモーションの一環です。
ドラマは仕事と私生活の記憶を分離する手術を受けた主人公を描くSFスリラーです。
-
-
-
マイクロソフトが業務ソフト向けの生成AIを自社開発する方針を表明しました。
OpenAIとの提携に加えて、独自のAI開発を進めることで、競争力を高める狙いがあります。
これにより、ビジネスにおけるAI活用がさらに加速することが期待されます。
-
-
-
トヨタなど24社が参加するAIロボット協会が発足しました。
この協会は、AIとロボット技術を融合し、汎用ロボットの実現を目指します。
大規模なロボット稼働データを収集し、共有する枠組みを構築します。
-
-
-
JAWS DAYS 2025でAWSのセキュリティ運用の自動化について講演した内容を紹介しています。
FW系リソースの自動更新やGuardDuty Malware Protection for S3の活用について解説。
Configを活用した自動修復機能とそのポイントについても触れています。
-
-
-
この海外記事は、AIエージェントのツール統合における課題と、AnthropicのMCPがその解決策となり得る理由を解説。
MCPは、オープンスタンダードとして、ツール間の相互運用性を高め、開発者が高品質なツールを容易に発見・利用できるようにすることを目指しています。
Mastraは、MCPの採用を推進し、エージェントフレームワークでのシームレスな統合を目指しています。
-
-
-
Cursorに複数の人格を入れることで、プロダクトマネジメントの壁打ち相手として活用できるという記事です。
稲盛和夫さんの考え方を参考に、楽観的な構想、悲観的な計画、楽観的な実行という人格をAIに持たせています。
ユーザー視点を取り入れるために、ユーザーペルソナを読み込ませて意見を求める活用例も紹介されています。
-
-
-
AI技術を使って、歴史的な事件や自画像など、あらゆるものをジブリ風に変換する「Ghiblification」が世界中で流行しています。
この技術は、誰もが手軽にジブリ作品のような美しい画像を生成できるため、SNSを中心に大きな話題を呼んでいます。
ユーザーは、様々な画像をジブリ風に変換し、その結果を共有して楽しんでいます。
-
-
-
LayerXのエンジニアブログで、生成AIプロダクト開発におけるQAエンジニアの役割について解説されています。
生成AI特有の評価指標やテスト戦略、プロンプト設計へのQA介入の重要性が述べられています。
AI技術が中核となる現場で、ビジネス価値を最大化するためのQAの役割が強調されています。
-
-
-
最新のAI技術で写真をジブリ風に変換することが、海外で非常に人気を集めています。
無料版のChatGPTでも試せるものの、有料版の方がより高品質な結果が得られるようです。
家族写真や風景写真をジブリ風にすることで、新たな楽しみ方が広がっています。
-
-
-
富士通が基幹システムのOS更新に生成AIを活用し、作業時間を65%削減した事例を紹介しています。
三井住友銀行(SMBC)向けシステムでプログラムの互換性問題を生成AIで抽出し効率化。
トヨタグループ向け基幹システムでも成果を上げており、他の案件でも実証実験中です。
-
-
-
RubyMineを長年愛用していた開発者が、AI搭載エディタCursorを導入し併用しています。
Cursorの導入により、特にClaude 3.7 Sonnetのリリース以降、機能実装の効率が向上しました。
RubyMineの優れた全文検索UIや正確なコードジャンプ機能も再認識し、併用による効率化を図っています。
-
-
-
この記事では、PHPでMCPサーバーを作成する方法について解説されています。
SDKがないため、実装は容易ではないことが述べられています。
MCPサーバー構築に挑戦したいPHP開発者にとって参考になるでしょう。
-
-
-
この記事は、LangGraphを利用したManusの再現実装であるLangManusについて解説しています。
LangManusを参考に、シンプルなAIエージェントを構築する方法を学ぶことを目的としています。
LangChainとLangGraphを理解していることを前提に、LangManusの構造やシンプルなAIエージェントの構造、コード、実行結果について詳しく解説します。
-
-
-
この記事では、ベクトル解析を微分形式で置き換える試みについて考察しています。
マクスウェルの応力テンソルを例に、微分形式ではカバーできない計算があることを指摘しています。
ベクトル値の微分形式と共変外微分を導入し、String Diagramを用いた計算方法を提案しています。
-
-
-
UE5でランナーゲームを作成する過程を紹介しています。
株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&Rクリエイティブスタジオ)TAチームによるものです。
ゲーム開発のノウハウが詰まっています。
-
-
-
クラウドエース株式会社の公式技術ブログ記事です。
Cloud Spannerの開発について解説されています。
商品名やサービス名は各社の商標または登録商標である旨が記載されています。
-
-
-
サブスクリプションの解約をほぼ自動化するサービスを開発した話。
クレジットカードの明細をアップロードするだけで、AIがサブスクを特定し、解約ページへのアクセスから解約手続きまでを自動化します。
OpenAIのResponses APIとComputer Use機能を活用し、ユーザーの負担を軽減することを目指しています。
-
-
-
WebAssemblyを利用した画像変換について紹介されています。
マルチスレッドを使用することで処理を並列化し、高速化を実現しています。
ブラウザだけでなく、Node.jsやDenoなど他の環境でも利用可能です。
-
-
-
この記事では、カラー設計とアクセシビリティについて解説しています。
FigmaのVariablesとFlutterのThemeExtensionを活用したカラー管理方法を紹介しています。
アクセシビリティテストの実装例も掲載されており、実践的な内容です。
-
-
-
Google Docsのチームでのバグトリアージについての海外記事。
致命的なエラーの原因を調査し、Chromeの特定バージョンで発生していることを特定。
最終的にV8エンジンの最適化パスにおけるMath.abs()関数のバグが原因と判明した。
-
-
-
Linuxコンテナランタイムをスクラッチから構築したStyroliteの紹介記事です。
従来のコンテナ作成方法と比較して、Styroliteがコンテナ作成をどのように簡素化するかを解説しています。
セキュアなマイクロサービス、アプリケーションサンドボックス、カスタムCI/CD環境など、Styroliteの実際のアプリケーションを紹介します。
-
-
-
Apple MusicがDJ向けの新機能「DJ With Apple Music」を発表しました。
これにより、Apple Musicの膨大な楽曲ライブラリを活用して、DJは直接ミックスを作成できます。
主要なDJソフトウェアやハードウェアとの連携も強化され、より創造的なDJ体験が可能になります。
-
-
-
この海外記事では、政治家が現状を打破するまで、豊かさは実現しないと主張しています。
住宅、移民、クリーンエネルギーインフラなど、あらゆるものを増やす必要があると述べています。
政府が具体的な成果を上げられない場合、現状維持は有権者によって罰せられると警告しています。
-
-
-
この記事では、UIにおけるアンドゥ機能の実装について解説されています。
アンドゥスタックとバージョン履歴の2つの形式を紹介し、アンドゥスタックの実装に焦点を当てています。
JavaScriptでの実装例を通じて、インデックスを使用しない効率的なアンドゥスタックの構築方法を提案しています。
-
-
-
DeepSeek-V3についての技術論文。
671Bのパラメータを持つMoE言語モデルで、各トークンに対して37Bがアクティブになる設計です。
効率的な推論とコスト効率の高いトレーニングを目的としています。
-
-
-
C23規格に対応したModern Cに関する情報です。
新しい規格に対応するための変更点や追加機能が解説されています。
整数型、nullptr、属性、型推論、constexprなどが含まれます。
-
-
-
このリポジトリは、1972年に登場した最初のCコンパイラのソースコードが収められています。
現代のCコンパイラ(例えばgcc)では、この古いソースコードがコンパイルできないようです。
-
-
-
Dagger Shellは、コンテナ時代の新しいシェルとして、DockerやMakeなどの良い点を統合しています。
コンテナ、シークレット、サービスエンドポイントなどのプリミティブをネイティブにサポートし、型付きオブジェクトや宣言的な実行を可能にします。
Dagger Engineのbash構文フロントエンドとして、ビルド、テスト、デプロイメントなどのタスクを自動化します。
-
-
-
この記事では、Rustにおける動的ディスパッチについて解説されています。
特に、複数のトレイト境界を持つトレイトオブジェクトの実現方法について考察されています。
C++との比較や、vtableの構造、トレイト継承の制限など、詳細な分析が述べられています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より