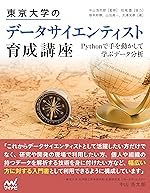-
-
大阪・関西万博での空飛ぶクルマの商用運航は全陣営が断念しました。
日本航空はデモ飛行すら断念し、機体模型の展示のみとなります。
SkyDriveやANAなどはデモフライトを予定しており、万博後の実用化に向けた計画も発表されています。
-
-
-
アリババの動画生成モデル「Wan 2.1」の性能が非常に高いです。
ローカル環境でも高品質な動画が生成可能で、技術開発の動きが活発化しています。
動画生成AIにStable Diffusion登場時のようなインパクトを与えています。
-
-
-
Dagger Shellは、コンテナ操作をシェルから可能にする新しいツールです。
Docker創始者らが開発したDagger Engineを基盤とし、ワークフローを自動化します。
Go, Python, Typescriptなど多様な言語で拡張可能で、Daggerverseによる拡張もサポート。
-
-
-
この記事では、AIコーディングエージェント(Cline派生のRoo Code)を使用して、短期間で大量のコードを生成する実験について解説されています。
4日間で数ヶ月分のコードを生成できたものの、技術的負債が急速に蓄積される問題に直面し、その解消に焦点を当てています。
技術的負債の解消には、一度に一つの明確な課題に集中し、シンプルなリファクタリングを徹底することが効果的であると結論付けています。
-
-
-
この記事では、不要になったノートPCの処分方法を検証しています。
PCリサイクルマークの有無やPCの状態によって手順が異なることを解説しています。
パソコン3R推進協会とリネットジャパンという2つの処分方法を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを比較しています。
-
-
-
プライベート開催されたAIコーディングエージェント勉強会の資料です。
Clineを使用してコーディングを進めていく手順を、ステップ・バイ・ステップで解説。
勉強会は2025/3/25に開催されました。
-
-
-
増田の日記がAIによって生成されているという話。
それをさらにbotがブックマークするという状況。
地獄のような光景だと表現されています。
-
-
-
この記事では、営業AIエージェント「アポドリ」でのDify活用事例を紹介しています。
Difyを導入したことで、プロンプトの変更が容易になり、ドメインエキスパートが開発に参加しやすくなりました。
プロンプトエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアリング、ドメイン知識の統合がDifyによって促進されています。
-
-
-
VMware Workstation Proの無償化が発表されました。
公式サイトからのダウンロード手順が非常にわかりづらいので、手順がまとめられています。
仮想マシンの作成手順も解説されており、導入の参考になります。
-
-
-
マイクロソフトが仮想化ハイパーバイザ上でWasmを高速起動する「Hyperlight Wasm」を公開しました。
Hyperlightは仮想化ハイパーバイザ上にマイクロゲストを作成するライブラリで、OSのオーバーヘッドを削減します。
Hyperlight Wasmは、Wasmtimeを用いて仮想マシンやOSを介さずにWebAssemblyランタイムを高速に起動します。
-
-
-
スティックのりのUIに関する話題のまとめ。
UIが分かりにくいという意見と、そうではないという意見が交錯。
セブンのコーヒーマシン現象という例えも登場。
-
-
-
はてラボ人間性センターが終了しました。
スパム対策が別の方法で実現されたためです。
今後は別の方法でスパム対策が行われます。
-
-
-
QualcommのXPANは、イヤフォンのワイヤレス伝送にWi-Fiを導入する画期的な技術です。
Bluetoothに代わり、Wi-Fiの広い帯域幅を活かして高音質を実現し、接続範囲を拡張します。
将来的には、イヤフォンが直接インターネットに接続できる可能性も秘めています。
-
-
-
公正取引委員会は、スマホのOSやアプリストアを手掛ける企業を規制する法律の対象企業として、GoogleとAppleを指定しました。
この法律は、スマホ関連市場の競争促進を目的としており、違反した場合は課徴金が課せられます。
Appleはプライバシーと安全面での懸念を表明し、Googleは公平な事業環境の確保に努める旨の声明を発表しています。
-
-
-
この記事では、ChatGPTで生成した絵から3Dモデルの部品を大量に生成する方法を紹介しています。
ChatGPTの画像生成機能を活用し、オブジェクトの絵をバラバラに出力します。
ローカルのimage to mesh技術を用いて、一貫性のある3Dモデルを大量に作成する手順を解説します。
-
-
-
この記事は、3年目までのエンジニアに向けて技術ブログの書き方を解説しています。
ブログを書く意義や種類、書き方のポイントを丁寧に説明しています。
記事の構成や読みやすさのテクニック、反発を受けた時の心構えも学べます。
-
-
-
この記事では、UEFIブートキットの基礎と、実際の攻撃事例を解説しています。
ブートキットがBIOSに感染するメリットや手法、そしてセキュリティ対策の重要性を説明しています。
特に、安全保障、クラウド、TEE環境におけるBIOSセキュリティの重要性を強調しています。
-
-
-
ヒューマノイドロボット「Figure 02」に人間のような歩行を教えることに成功したという記事。
強化学習を利用し、自然な歩行を実現しています。
大量のロボットが行進する様子は少し不気味でもあります。
-
-
-
17.3型なのにコンパクトに折りたためるポータブルモニター、ASUS「ZenScreen Fold OLED」のレビュー記事です。
折りたたみ時は12.5インチ、展開すると17.3インチの大画面として利用可能で、携帯性と作業領域の広さを両立しています。
Type-C接続で手軽に利用でき、別売りのモニタースタンドを使えばさらに快適な作業環境を構築できます。
-
-
-
エムスリーのプロダクトマネージャーの松尾氏が、入社後の学びを共有しています。
プロダクトマネージャーにとって「ビジョン」が重要であることに気づいたそうです。
自身の思考タイプ「ビジュアルシンカー」を活用し、課題発見やコミュニケーションに役立てています。
-
-
-
この記事では、USB端子をPS/2コネクタに変換するアダプターの仕組みを解説しています。
Microsoftの開発者が、その内部構造と動作原理を詳しく説明しています。
過去の技術に触れつつ、現代のデバイスとの互換性について考察しています。
-
-
-
この記事では、Amazon Route 53プロファイルを使用して、AWS PrivateLinkのDNS管理を効率化する方法を紹介します。
PrivateLinkは、VPCとAWSサービス間のプライベート接続を可能にし、Route 53プロファイルはDNS管理を簡素化します。
複数のAWSアカウントやオンプレミス環境でのPrivateLink展開を容易にし、コストと運用オーバーヘッドを削減します。
-
-
-
この記事では、GoogleのLLM「Gemini」を活用したGitHub Actionsによるコードレビューの自動化について解説します。
Gemini APIとGitHub Actionsを組み合わせ、コードの正確性、効率性、保守性、セキュリティなどを自動でチェックする仕組みを構築します。
具体的な設定方法やプロンプトの例も紹介されており、開発効率の向上に役立つ情報が満載です。
-
-
-
この記事は、ジュニアエンジニアからシニアエンジニアになるまでに筆者が実践してきたことをまとめたものです。
Pull Requestのセルフレビューや趣味プロジェクトの実施、地味な改善活動など、真似しやすいものから体力のいるものまで紹介されています。
アウトプットを継続することの重要性も強調されています。
-
-
-
この記事では、.NETでHttpClientを安全かつ効率的に使用する方法を解説しています。
HttpClientの基本的な使い方から、IHttpClientFactoryや名前付きクライアント、型指定クライアントの利用までを網羅的に説明しています。
シングルトンサービスでのHttpClient利用時の注意点と、DNS変更への対応策も紹介されています。
-
-
-
ミャンマー大地震に関連し、生成AIで作られた偽動画がSNSで拡散されています。
仏教寺院の倒壊動画には生成AIサービスの透かしがあり、複数の言語で拡散されています。
災害時には偽情報が広がりやすいので、安易な拡散に注意が必要です。
-
-
-
「ChatGPT Team」に社内データを利用する新機能が追加されました。
これにより、ChatGPTは社内データに基づいてより的確な応答が可能になります。
ZDNET Japanの記事で詳細が解説されています。
-
-
-
情シスがDX推進の前に業務標準化を提案したものの、
現場との対立を招いているという記事です。
現場が慣れるまでのリハビリか、改革を強行するかの選択肢が提示されています。
-
-
-
Webアクセシビリティの実務対応について解説します。
2012年からフロントエンドエンジニアとして活躍されている著者による書籍です。
アクセシビリティ対応のノウハウが詰まっています。
-
-
-
この記事は、創業期のスタートアップに入社した5ヶ月間を振り返ったものです。
プロダクト開発以外に行った改善活動について、ドメインモデリングの導入やコミュニケーションの促進などが紹介されています。
開発者体験の向上やアーキテクチャの見直し、技術広報の準備など、多岐にわたる取り組みが語られています。
-
-
-
M5Stack社のLLMモジュールをCoreシリーズなしで単体動作させる方法を解説しています。
Linuxシステムとしてシェル操作を行い、各ユニットを初期化してAIと対話します。
ウェイクワードを検出し、音声認識とテキスト生成を経て音声合成を行うPythonスクリプトを紹介しています。
-
-
-
Next.js App Routerを使用した技術スタック共有サイトのサンプルアプリ構築に関する記事です。
ORM(Prisma)を用いたDBアクセス、簡易的なテスト、Next.js特有のモーダル実装、認証認可、OpenTelemetryによる計装について解説されています。
技術選定から実装、テスト、デプロイまでの一連の流れがまとめられており、Next.jsでのフルスタック開発の参考になります。
-
-
-
React19の安定版についてコードで比較し解説しています。
React19に関する情報が無料で読めます。
Reactをより深く理解したい方におすすめです。
-
-
-
この記事では、JavaScriptのPromiseがモナドではない理由を2つの観点から解説しています。
1つ目はPromiseの入れ子に着目し、left identityが破れることを示しています。
2つ目は例外の扱い方に着目し、例外を巡る仕組みを利用することでもモナド則を壊せることを紹介しています。
-
-
-
この記事ではChromebookで情報オリンピックに挑戦するための環境構築について解説します。
Linux環境と必要なソフトウェアのインストール手順が説明されています。
Chromebookユーザーが競技プログラミングを始めるための有用な情報源となるでしょう。
-
-
-
Karabiner-Elementsでタップダンスとレイヤーを組み合わせる方法を解説しています。
かなキーを2回押すとレイヤーに移行する設定や、右OptionキーのダブルタップでLayer1をONにする設定を紹介。
Complex Modificationsの基本から、レイヤー、タップダンス、そして両者の組み合わせまでを丁寧に解説しています。
-
-
-
FreeCADとClaudeを連携させて、LLMによるCAD設計支援の可能性を探る試みを紹介しています。
自作のFreeCAD用MCPサーバを使用し、様々な設計を試しています。
2D図面からの3DCAD生成やCAEのデモなど、興味深い結果が得られています。
-
-
-
M5Stack + Module LLMを使ってみた記事です。
このモジュールは、M5Stackにスタックして使うことができるAI処理用のモジュールです。
LLMに限らず、画像処理や音声認識、音声合成などのAI処理をデバイス内で行うことができます。
-
-
-
この記事では、エンジニア目線でよく見かけるウェブアクセシビリティ違反の例を紹介しています。
キーボード操作、フォーカスのコントラスト、レスポンシブ対応、停止できないカルーセルなど、具体的な問題点と改善策を解説。
ウェブアクセシビリティ向上が、ユーザー体験の向上と情報アクセスの平等につながることを強調しています。
-
-
-
この記事では、GitHub CLIのおすすめの使い方について紹介されています。
特に、ターミナルでの操作に慣れていない人に向けて、スニペット例を通じてGitHub CLIの活用イメージを伝えています。
PR操作、ステータス確認、ブラウザでのリポジトリ表示など、具体的なコマンド例が掲載されています。
-
-
-
尊敬するエンジニアがClineを使い始めているという記事です。
時代の変化を感じさせる一方、認知負荷の問題も提起されています。
人間の限界に挑戦するような状況になっているようです。
-
-
-
この海外記事は、トランプ政権によるアメリカ合衆国憲法修正第1条への攻撃について解説しています。
言論の自由、報道の自由、集会の自由、請願の権利、信教の自由の5つの柱が脅かされています。
具体的な事例を挙げながら、各権利がどのように侵害されているかを詳述しています。
-
-
-
Chrome 135から、CSSでカスタマイズ可能な`<select>`要素が利用可能になりました。
`appearance: base-select`を使用すると、多くの新機能が利用できます。
`<select>`要素に画像やSVGなどのリッチなHTMLコンテンツを含めることができるようになりました。
-
-
-
1980年代にはラジオからゲームをダウンロードしていたという海外記事。
当時、家庭用コンピュータでゲームを遊ぶには、ラジオ放送をカセットテープに録音する必要がありました。
BASICODEという規格のおかげで、異なる機種のコンピュータでも同じようにゲームを楽しめました。
-
-
-
WhatsApp MCPサーバーに関するGitHubリポジトリです。
このサーバーを使うことでWhatsAppの機能を拡張できる可能性があります。
詳細な機能や使い方はリンク先のリポジトリをご確認ください。
-
-
-
この海外記事では、IMAP4プロトコルを使用してメールサーバーと通信する方法を解説しています。
telnetやOpenSSLを使ってメールサーバーに接続し、ログイン、フォルダのリスト表示、メールの検索、内容の取得などの基本的な操作をコマンドラインから実行できます。
メールの送受信にはSMTPを使用しますが、この記事ではIMAPに焦点を当てています。
-
-
-
C/C++コンパイラ向けのセキュリティ強化オプションについて解説されています。
コンパイル時および実行時の脆弱性検出、OSのセキュリティ機能との連携などが目的です。
GCCとClangを中心に、具体的なオプションとその効果、注意点などを網羅的に紹介しています。
-
-
-
ブラウザ上でMinecraft 1.2.5を動作させるデモです。
CheerpJというJava実行環境を使用し、オリジナルのJARファイルを修正せずに実行しています。
オーディオはまだサポートされていませんが、今後の改善に期待できます。
-
-
-
Microsoft Azure CLIに対するパスワードスプレー攻撃の事例を紹介しています。
攻撃者は24人のユーザーを標的とし、各ユーザーに対して2回以下のログイン試行に留めています。
テナント全体のログイン状況を分析することで、個々のユーザーの活動だけでは見逃してしまう攻撃を検出しています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より