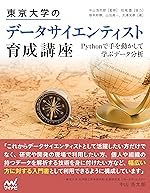-
-
この記事では、エンジニアがチーム開発でより円滑なコミュニケーションを取るためのベストプラクティスを紹介しています。
レビュー時のWhyの明記、議論での共通認識の重視、報告・連絡・相談における情報公開など、具体的なプラクティスが示されています。
これらのプラクティスは、チームの生産性向上と組織全体の目標達成に貢献することを目指しています。
-
-
-
ChatGPTの画像生成機能が無料で利用可能になり、AI業界に革新をもたらしました。
簡単なプロンプトでイメージ通りの画像を生成でき、生成後の修正も容易です。
イラスト生成だけでなく、実写風画像やグラフィックレコーディングも得意としています。
-
-
-
この資料はPostgreSQLアンカンファレンス@オンラインの登壇資料です。
PostgreSQLをAIの力を借りて改善するPgAssistantの紹介をしています。
データベースエンジニアの仕事を楽にするツールです。
-
-
-
ChatGPTの新しい画像生成機能が利用急増により、無料ユーザー向けの展開が一時延期となりました。
OpenAIのCEOはGPU負荷の高まりを理由に挙げています。
今後は効率化を図りつつ、無料ユーザーにも1日3回までの画像生成を提供する予定です。
-
-
-
Anthropicが大規模言語モデルClaudeの思考の軌跡を可視化する研究を発表しました。
言語を超えた概念空間での思考や、韻を踏む語を事前に想定する能力などが明らかになりました。
AIの内部構造を解析し、信頼性と安全性を高める重要性が述べられています。
-
-
-
NHKが日本IBMを提訴し、富士通製メインフレームの刷新プロジェクトが頓挫した件についてです。
クラウド基盤への移行を日本IBMに委託したが、納期遅延により契約解除、NHKは54億円の損害賠償を請求しています。
日本IBMは真っ向から反論しており、今後の裁判で両社の主張が展開される見込みです。
-
-
-
この記事では、小型化・薄型化に特化した5つのミニマウスを紹介しています。
ボディがないボタンだけのマウスや、超小型・超薄型のマウス、ホイール搭載ながらフラットなマウスなど、ユニークな製品が揃っています。
持ち運びやすさや省スペース性、操作性など、それぞれの特徴を比較検討できます。
-
-
-
この記事では、ネットワーク構成図をコードで自動生成する方法を紹介しています。
Pythonスクリプトを使用し、draw.io形式のXMLファイルを生成しています。
これにより、ネットワーク構成の変更を容易に管理し、可視化できます。
-
-
-
海外のAIアプリ関係者がジブリから著作権侵害警告を受けたと投稿。
しかし、その警告文の画像自体がフェイクであるという指摘が出ています。
話題を利用した自社製品のPRだった可能性も浮上し、騒動となっています。
-
-
-
この資料は、エラーハンドリングの設計に関するプレゼンテーションです。
独自のオブジェクトやResult型を用いたエラー表現について解説しています。
throw/try-catch, コールバック、Promiseなど、エラー伝達方法についても触れています。
-
-
-
Kubernetes環境におけるPrometheusを用いた監視の仕組みをハンズオン形式で解説しています。
PrometheusがKubernetesの情報をどのように収集しているかを体験的に理解できます。
サービスディスカバリの仕組みやExporterの役割など、Prometheusの基本を学べます。
-
-
-
マイクロソフトのキャラクター「カイル君」のアクリルスタンド風カプセルトイが発表されました。
3月27日開催の「Microsoft AI Tour Tokyo」で会場限定カプセルトイとして提供されます。
カイル君はネットミームとして親しまれており、今回のカプセルトイ化はXで寄せられた意見を受けた企画です。
-
-
-
ChatGPTの画像生成機能でジブリ風画像が急増しています。
OpenAIのCEOが自身のプロフィール画像をジブリ風に変更し、著作権侵害の疑いが浮上しています。
宮崎駿監督はAIによる表現に対し、生命に対する侮辱だと激怒しています。
-
-
-
この記事では、カンファレンスブース設計の秘訣を紹介しています。
参加者との対話を最優先にし、カンファレンスのテーマやコンセプトを尊重することが重要です。
ブースを出す目的を明確にし、ゴールへの流れを作ることで効果的なブース運営を目指します。
-
-
-
LLM(大規模言語モデル)を活用する際に、制約を設けることで創造性を高める方法について解説されています。
特に、ALPSというWebサービスの挙動やデータ要素を記述するフォーマットを使用し、Devin AIとの連携事例を紹介しています。
制約をデザインすることで、人間とAIが共通言語を持ち、効率的な開発が可能になることを示唆しています。
-
-
-
Oculusの元CEOが立ち上げたSesameの音声AIが話題になっています。
このAIはほぼ人間の様に自然な会話を実現し、不気味の谷を超えたと評されています。
感情を把握し、文脈に応じた応答や人間特有の不完全さを模倣する点が特徴です。
-
-
-
SmartHR最大のRailsアプリケーションにYJITを導入し、パフォーマンスが向上しました。
レスポンスタイムが最大18%減少し、コードの約98%がYJITで実行されるようになりました。
RailsやRubyへのコントリビュートも行い、YJIT導入に関する知見を共有しています。
-
-
-
フロントエンドテストに関する発表資料です。
JestとStorybookを活用したテスト手法を紹介しています。
コンポーネントのテスト方法について具体的に解説されています。
-
-
-
大阪にある13坪の小さな本屋、隆祥館書店を紹介しています。
店主の二村知子さんが、いかにして本を売り、書店を存続させてきたのかを解説。
アナログな手法と本への情熱が、アマゾンには真似できない強みとなっているようです。
-
-
-
M4チップ搭載の新型MacBook Airが発売されました。
15インチモデルは19万8,800円からで、最小メモリ容量が16GBに引き上げられています。
最大3画面表示や12MPセンターフレームカメラなど、使い勝手が向上しています。
-
-
-
Minisforum MS-01は拡張性と接続性に優れた小型PCです。
10G SFP+ポートを2つ搭載しており、高速なネットワーク構築が可能です。
Intel AMTの設定についても解説されています。
-
-
-
総務省はLINEヤフーに行政指導を行ったと発表しました。
LINEアルバムで他人の写真のサムネイルが誤表示される不具合が発生したことが原因です。
総務省は再発防止の徹底などを求めています。
-
-
-
日野市で計画されている大規模データセンターの建設に対し、住民から反対運動が起きています。
事業主である三井不動産は、住民の意見を考慮し計画の一部変更を発表しました。
住民は、住宅地との近さや排熱による環境への影響を懸念しています。
-
-
-
量子コンピュータを用いて予測困難な乱数生成に成功した研究を紹介しています。
古典コンピュータでは不可能な計算速度で、公平な乱数を作り出すことに成功しました。
オンライン宝くじや電子ゲームなど、公平性が求められる場面での応用が期待されています。
-
-
-
組織内の課題や改善提案を気軽に投稿できる目安箱の設置について解説されています。
投稿が放置されずに改善につながるポイント、感謝される仕組みが重要です。
投稿のハードルを下げ、投稿するメリットを感じられるようにすることで、形骸化を防ぎ、活発な意見交換を促します。
-
-
-
この記事では、Figma MCPとAI搭載コードエディタCursorを組み合わせたUI実装の加速について解説しています。
チームでの導入背景から実装ステップ、運用上の工夫、成功事例と課題点を共有。
精度向上のための具体的な工夫として、cursor_rulesの活用や既存実装の参照などを紹介しています。
-
-
-
Google Cloud主催のSecOps Partner向けイベントの参加レポートです。
Google Threat Intelligence (Google TI) の機能や活用方法について紹介されています。
ワークショップの内容やCTFの結果などがまとめられています。
-
-
-
この記事では、AIによって生成されたコードを理解することの重要性について議論されています。
AIが生成したコードには脆弱性や誤ったゴール設定のリスクがあり、人間の開発者がコードを理解し、修正する必要があります。
AIを道具として使いこなしつつ、コードを丸投げしない姿勢が重要であると結論付けています。
-
-
-
OpenAIの画像生成機能とSoraの利便性について解説されています。
ビジネスでの活用例として、グラレコ作成や現場での告知、風刺漫画などが紹介されています。
Soraのプリセット機能やライブラリ管理、アスペクト比指定などが便利だと述べられています。
-
-
-
MCPの新しい仕様が策定された件について、NotebookLMに投入する手順が記載されています。
GitHubのURLをuithub.com経由でアクセスすると、LLMに食わせるためのテキストに変換できます。
変更履歴を知りたい場合は、changelog.mdから追うのが良いでしょう。
-
-
-
この記事では、FlutterとAIツール(Cline、Windsurf)を活用した植物日記アプリの開発プロセスを紹介しています。
プロンプトの作成、AIによるアプリの自動生成、UIの改善、収益化実装、多言語対応、ストア申請など、リリースまでの全工程を解説。
AIを活用することで、開発期間を短縮し、コストを抑えつつ、高品質なアプリを開発できることを示しています。
-
-
-
バージニア州の田舎道を300マイル運転し、警察に車の監視映像を要求した結果についての記事。
警察はFlock LPRカメラを使用して、人々の行動を監視している。
個人の行動が予測可能になる可能性や、プライバシーに関する懸念が提起されている。
-
-
-
ソーシャルメディアはもはや社会的なものではなく、質の低いコンテンツの競争になっていると筆者は述べています。
プラットフォームは収益化のためにクリックやインタラクションを重視し、創造性や信頼性を阻害していると指摘しています。
AIによるコンテンツ作成が容易になった現在、お金や影響力を求めるのではなく、喜びや他者への貢献を重視すべきだと提唱しています。
-
-
-
Appleは、MacOS SequoiaとiOS/iPadOS 18の品質改善をすべきだと主張しています。
メッセージアプリのコピー&ペーストの不具合や、Mailアプリの接続問題など、多くのバグを指摘しています。
AI開発競争に遅れている現状を打破するためにも、まずは足元を固めるべきだと述べています。
-
-
-
3歳から5歳の子どもを対象にした研究で、子供達は日用品を整理する際に高度な数学的思考を使っていることがわかりました。
子供達は、色や形などの基準に基づいて物を分類し、一貫性がない場合は自発的にグループを調整します。
この研究は、適切なサポートがあれば、子供達は幼い頃から高度な数学的推論を発達させることができると示唆しています。
-
-
-
この本は、Pythonでの複雑なビジネス問題を解決するためのアーキテクチャパターンを紹介しています。
TDD、DDD、イベント駆動アーキテクチャをサポートする方法を解説し、Pythonらしい実装を目指しています。
具体的な技術選択が重要ではなくなるようなアーキテクチャを構築することを目標としています。
-
-
-
この記事では、AI時代におけるコーディングの学習について考察しています。
AIの進化によりコーディングが不要になるという意見に対し、著者は基礎の重要性を強調しています。
AIに頼りすぎるとベンダーにコントロールされ、将来の選択肢を狭める可能性があると警告しています。
-
-
-
企業の見栄っ張りの時代は終わりに近づいているという記事です。
オフィス回帰の指示は、データよりもエゴや金銭が関係していると指摘しています。
柔軟な働き方を許容することで、従業員と雇用主の両方が利益を得ると述べています。
-
-
-
Sonic Advance 2のC言語によるGameBoy Advanceゲームの逆コンパイルと移植に関する情報です。
このプロジェクトはGitHubで公開されています。
詳細については、リンク先のリポジトリをご覧ください。
-
-
-
この記事は、電子回路の自動配線(autorouter)を開発する前に知りたかった13の事柄をまとめたものです。
A*アルゴリズムの重要性、空間ハッシュインデックスの利用、キャッシュの活用など、実践的なアドバイスが満載です。
JavaScriptでの開発、問題の可視化、再帰関数の回避など、具体的なテクニックも紹介されています。
-
-
-
この記事は、emダッシュ、enダッシュ、ハイフンの正しい使い方を解説しています。
emダッシュは文の区切りや強調、enダッシュは範囲を示す際に使用します。
ハイフンは単語の連結や分割、文字のスペルアウトなどに用いられます。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より