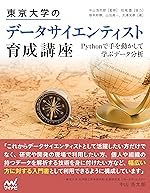-
-
MicrosoftはWindows 11の全エディションでMicrosoftアカウントを必須に変更しました。
これにより、ローカルアカウントのみでのセットアップが不可能になります。
プライバシーを重視するユーザーにとっては懸念材料となる可能性があります。
-
-
-
Windows 11の最新ビルドで、Microsoftアカウントなしでインストールするためのスクリプト「bypassnro.cmd」が削除されました。
しかし、インターネット接続とMicrosoftアカウントの要件を回避する代替手段が発見されています。
コマンドプロンプトから特定のコマンドを実行することで、同様のスキップが可能になります。
-
-
-
ChatGPTのプロンプトを特許の請求項のように記述すると、特定のキャラクターが生成されるという実験。
実験では、人気漫画のキャラクター「イカ娘」に酷似したものが生成されたとのことです。
プロンプトの記述方法によってAIの生成結果が大きく変わる可能性を示唆しています。
-
-
-
AIにスーツを着せてもらい証明写真を作成した記事。
志望動機や自己PRもAIに考えてもらったとのこと。
面接に挑んだ結果がどうなったのかがまとめられています。
-
-
-
はてなブックマークの終焉に関する記事です。
かつての隆盛から、現在の状況に至るまでの経緯を考察しています。
SNSの変化とユーザーの移行が背景にあるようです。
-
-
-
AIアニメについて専門家が酷評したという記事です。
服装やサイズがバラバラであることを問題視しています。
しかし、AIアニメが専門家から相手にされる次元になったという反響も呼んでいます。
-
-
-
生成AI技術の最新動向を紹介する記事です。
スマホカメラから3D空間を理解するSpatialLM、静止画を3Dビデオに変換するStable Virtual Cameraなどが解説されています。
高解像度3Dメッシュ生成AIモデルDeepMeshや、動画のカメラ軌道再生成AIモデルReCamMasterも取り上げられています。
-
-
-
Clineは非常に便利なツールです。
ENECHANGE I/O Day アウトプット大会での発表資料です。
お金が飛ぶほど便利であることが語られています。
-
-
-
OpenAI Agents SDKで複数のMCPサーバーをツールとして利用する方法を紹介しています。
FilesystemとSlackのMCPサーバーを連携させたコード例とその準備手順を解説しています。
エージェントがファイルシステムとSlackワークスペースにアクセスするデモを通して、その可能性を示唆します。
-
-
-
プロダクトマネージャーが成果を出すために必要な「イシュー度の高い課題」を見極める方法について解説しています。
問題解決の成功は、問題を適切に設定できるかどうかでほぼ決まるという考え方を紹介しています。
ロードマップ策定、ユーザーインタビュー、データ分析への応用方法を具体的に説明しています。
-
-
-
TypeScriptで日本語文法を学べるリポジトリです。
文法の型定義がされているため、より深く理解できます。
GitHubで公開されており、コントリビューションも可能です。
-
-
-
iPhoneの電話録音機能とNotebookLMを連携させた活用事例を紹介しています。
カスタマーサポートとのやり取りを録音し、NotebookLMで内容を効率的に記録・分析する方法を解説。
トラブル解決の証拠としての活用や、議事録作成など応用的な使い方も提案しています。
-
-
-
CSSが効かない問題に2時間悩んだ経験が語られています。
先輩のアドバイスでChromeのシークレットモードを試したところ、すぐに解決したとのことです。
エンジニア界隈ではよくあることなのかどうか疑問を投げかけています。
-
-
-
この記事では、Go言語におけるインターフェースの概念と、そのクリーンアーキテクチャにおける重要性を解説しています。
PHPとの比較を通じてGoのインターフェースの特徴を明確にし、疎結合な設計が自然に実現できる点を強調しています。
具体的なコード例を交えながら、Goのインターフェースの実装方法と型アサーションについて詳しく説明しています。
-
-
-
AIアシスタントの進化により、エンジニアの役割が見直されています。
AIが得意な定型作業から、要件定義や設計など、より高度な判断が求められるようになります。
AIと協働し、ビジネス価値を創造できるエンジニアが、これからの時代に必要とされます。
-
-
-
丸の内にあるスパイスカレー店「Spice Theater Marunouchi」の紹介記事です。
札幌で人気だった「倉庫カリー」が前身で、本格的なインド・ネパール人シェフが作るカレーが売りです。
カレーの種類やメニュー、店内の様子などが写真付きで詳しく解説されています。
-
-
-
この記事では、RailsアプリケーションでSQLite拡張機能を読み込む方法を解説します。
Ruby gemとして提供されている拡張機能を簡単にインストールし、設定ファイルで指定することで利用可能にします。
開発環境でのSQLite利用を強化し、Gitブランチごとのデータベース切り替えと組み合わせることで、より柔軟な開発を支援します。
-
-
-
JaSST’25 Tokyo Day2で発表されたソフトウェア開発に関する資料です。
日本のソフトウェア開発における課題と、製造業の成功体験とのギャップについて考察しています。
現代のソフトウェア開発における歴史的背景を解説しています。
-
-
-
クレジットカードのサイン決済が2025年3月末で原則廃止されることが決定しました。
これは暗証番号入力が普及したことと、セキュリティ強化の一環です。
今後は、モバイル決済端末の導入などが推奨されています。
-
-
-
ChatGPT GPT-4oを活用し、手書きラフから広告を制作するフローが全公開されています。
AIとデザインを組み合わせ、外注費を抑えつつデザインの質を向上させる方法が紹介されています。
プロンプト例と共に、具体的な画像生成プロセスが解説されており、デザインスキル向上のヒントが得られます。
-
-
-
米国防長官が機密情報扱う会議に妻を同席させていたと報道されました。
会合には英国防相との会談やNATOのウクライナ支援を協議する会合が含まれます。
機密情報の管理を巡り、政権の新たな火種となる可能性があります。
-
-
-
この記事では、GeminiとGoogleドライブの連携による活用法を紹介しています。
Googleドライブ内のファイル検索、情報抽出、企画提案など、Geminiを活用した効率的な活用方法を解説。
無料のGeminiアプリやGeminiサイドパネルの活用方法、具体的なプロンプト例も紹介しています。
-
-
-
フォルクスワーゲンが物理ボタンを復活させるというニュースです。
デザイン責任者はタッチスクリーンへの過ちを繰り返さないと約束しています。
重要な機能は物理ボタンで操作できるようになるようです。
-
-
-
この記事では、プログラマー向けにバイブコーディングを加速するWindsurf代替ツール10選を紹介しています。
各ツールの特徴や利点、どのような開発者やプロジェクトに適しているかを詳しく解説しています。
Apidog MCPサーバーとの組み合わせによるAPI開発の効率化についても触れています。
-
-
-
2015年のAIによる職業代替リストが、2025年には真逆になっているという記事。
アナウンサーや漫画家など、代替可能性が低いとされた職業でAIの進化が著しい。
AIが手塚治虫氏の新作漫画のシナリオやキャラクターデザインを手掛けるプロジェクトも存在する。
-
-
-
この記事では、著者が以前使用していたMemory Bankというツールから、タスクリストに移行した経緯を紹介しています。
Memory Bankはコンテキストの切り替えに優れていましたが、タスク管理には不向きでした。
タスクリストを使うことで、より効率的にコンテキストを最適化できるようになったと述べています。
-
-
-
イタリア空軍参謀長が、P-1哨戒機の導入について言及しました。
これまでデフォルトだった米国製システムからの脱却を示唆しています。
国産技術の活用と、国際協力の可能性を模索する姿勢が伺えます。
-
-
-
牛尾剛さんがマイクロソフトで妥協を捨て、一流を目指す覚悟を語っています。
自身の経験から、戦略だけでなく深い理解の重要性を痛感したそうです。
変化の激しい時代を生き抜くエンジニアの覚悟が伝わる内容です。
-
-
-
GIGAZINEの記事で、現在のAI技術をスケールアップしても汎用人工知能(AGI)は開発できないと考える科学者の割合が76%に達するという調査結果が紹介されています。
この調査は、AI研究者の間でAGI開発に対する懐疑的な見方が広がっていることを示唆しています。
AIの進化に関する今後の議論に影響を与える可能性があります。
-
-
-
GitHubリポジトリをインタラクティブな図に変換します。
プロジェクトを迅速に視覚化するのに役立ちます。
GitHubのURLで'hub'を'diagram'に置き換えることも可能です。
-
-
-
この記事はJavaScriptの実行メカニズムについて解説しています。
イベントループを中心に、JavaScriptエンジンや外部環境APIとの連携を説明しています。
非同期処理の仕組みやタスク、マイクロタスクについても詳しく解説されています。
-
-
-
この記事では、近年脚光を浴びているModel Context Protocol (MCP)について解説されています。
MCPは、AIエージェントが外部のツールやデータソースと安全に双方向接続するためのオープンなプロトコルです。
MCPサーバーは、そのプロトコルに従って外部サービスの機能やデータを公開するサーバーを指し、生成AIの活用を促進する可能性を秘めています。
-
-
-
React Router v7の内部構造を解説した記事です。
リクエストからレンダリングまでの道のりを詳細に追っています。
Vite統合、Single Fetch、Lazy Loadingなどのキーとなる概念を深掘りします。
-
-
-
研究に役立つプログラミング情報を提供しています。
プログラミングスキルで研究の質を向上させましょう。
初心者でも安心して学べる内容です。
-
-
-
この記事では、話題のシェーダー言語SlangをRustとVulkan (ash)で試す方法を紹介します。
Slangの機能の一部を紹介し、RustとVulkanでSlangを使う際の設定方法を解説します。
NVIDIAやKhronos Groupが関わるSlangは、業界標準となる可能性があり、注目されています。
-
-
-
本記事では、特徴量ドリブンな MLOps を実現するための試みを紹介しています。
特徴量を第一級の資産として扱い、学習・推論・実サービスへの実装の一連のサイクルを自動化するものです。
これにより、モデルの品質を保証し、高速にモデル改善のサイクルを回すことを目指します。
-
-
-
この記事では、Luaの代替となるスクリプト言語についてまとめられています。
Lua向けのトランスパイラ言語から、非Lua VMの組み込み向けスクリプト言語まで幅広く紹介されています。
それぞれの言語の特徴や使用例が記載されており、Luaの代替を探している開発者にとって参考になる情報が満載です。
-
-
-
Go言語での単体テストにおける保守性の問題点を指摘しています。
モックを活用することで、内部実装への依存を減らし、テストが壊れにくい状態を目指す方法を紹介しています。
gomock, httptest, miniredisなどのライブラリを使った具体的な実装例と、テスタブルなコード設計について解説しています。
-
-
-
サイボウズのフロントエンドチームが毎週配信している記事です。
今回はForm Control Styling Level 1に関する情報が掲載されています。
フォームのスタイルをより細かく制御するための仕様について解説しています。
-
-
-
この記事では、Sentryのカスタムスパン計測機能を活用して、フロントエンドの内部処理のパフォーマンスを詳細にモニタリングする方法を紹介します。
SentryのstartSpan関数を使用すると、特定の処理にかかった時間を計測しSentryに送信できます。
継続的な計測と分析で、ユーザー体験の向上につなげましょう!
-
-
-
Go 1.24で導入されたtesting/synctestパッケージの使い方を丁寧に解説しています。
並列プログラムのテストにおける課題を解決するために実装された背景を説明しています。
Run関数とWait関数の具体的な仕様と動作を、サンプルコードとGoDocを基に解説しています。
-
-
-
このブログ記事では、ターミナルセッションを録画するためのツール「VHS」を紹介しています。
VHSを使うことで、アニメーションGIF、WebP、MP4などの形式で録画ファイルを作成できます。
また、好みの設定を固定したり、秘匿事項を隠したり、作業をファイルで分割したりするTipsも紹介しています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より